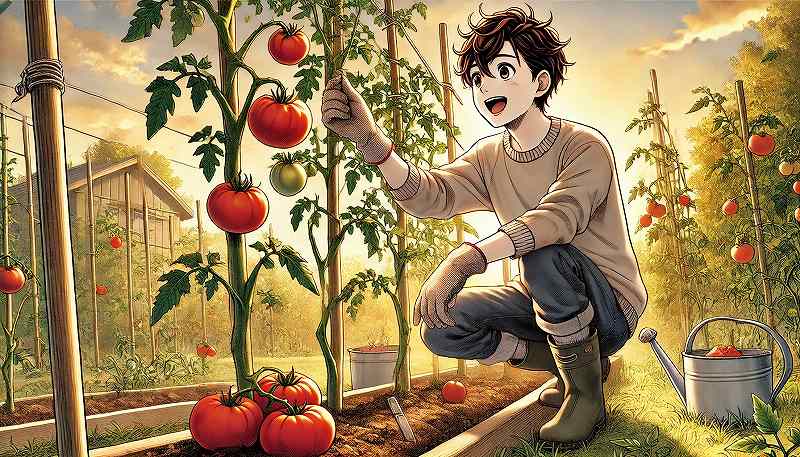「大玉トマトを育ててみたいけど、初心者でもできるの?」そんな不安を感じていませんか?
この記事では、初心者でも失敗しない大玉トマトの育て方を、手順やコツ、よくある失敗例まで、ぜんぶまるっと丁寧に解説します。
おすすめの品種や支柱の立て方、水やりのタイミングなど、家庭菜園デビューの方でも安心して取り組める情報が満載。
おいしくてジューシーな自家製トマトを育てたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
大玉トマトの育て方 初心者でも成功する5つの基本

大玉トマトの育て方 初心者でも成功する5つの基本について解説していきます。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
①苗はホームセンターで買うのがベスト

初心者さんにいちばんおすすめなのは、種から育てるのではなく苗を買ってくることです。
ホームセンターには春先になるとたくさんのトマト苗が並びますが、その中でも「接ぎ木苗」と書かれているものが特におすすめです。
接ぎ木苗は病気に強くて、根張りもしっかりしているので、失敗しにくいんです。
元気な苗を選ぶポイントは、「茎が太くて短め」「葉が濃い緑で密に生えている」「病斑や虫食いがない」といったところですね。
初心者のうちは、最初から元気な苗を選ぶことが収穫の近道ですよ~!
②日当たりと風通しの良い場所を選ぶ
大玉トマトはとにかく「日光が命」なんです。
一日中しっかり日が当たる場所じゃないと、実がつきにくくなるし、甘さも出にくくなります。
また、風通しも大切で、風が抜けない場所だと湿気がこもって病気の原因にもなるんですよね。
ベランダなら南向きがベストですが、どうしても日照時間が足りないときは午前中に光が入る場所を選びましょう。
プランター栽培の場合も同じく、風の通りと光の当たり方には要注意です。
③支柱は180cm以上でしっかり固定

大玉トマトはミニトマトに比べて背が高くなりやすく、実も重くなるので、支柱が必須です。
支柱の長さは最低でも180cm以上あると安心で、地面にしっかり差し込んで固定しましょう。
支柱がグラグラしていると、風が吹いたときに苗ごと倒れてしまうこともあるので要注意。
植えたタイミングで支柱を立てて、ヒモや園芸用テープで8の字にゆるく結んでいきます。
私も初めてのときは支柱が短すぎて途中で足りなくなったんですよ…なので最初から長めがおすすめです!
④わき芽かきと摘心を忘れずに
トマトを育てる上で絶対に外せない作業が「わき芽かき」と「摘心」です。
わき芽というのは、茎と葉の間に生えてくる小さな芽のことで、これを放置すると茎が増えてごちゃごちゃになります。
1本仕立てで育てたいので、わき芽はどんどん摘み取っていきましょう。
また、ある程度の高さまで育ったら「摘心」といって、茎の先端を切って成長を止める作業も必要です。
これをすることで、実に栄養がいってしっかり大きくなるんですよ~!
⑤水やりは朝にたっぷりと
水やりは朝のうちに、しっかりたっぷりあげるのが基本です。
夕方にやってしまうと、夜の間に湿気がこもってカビや病気の原因になることがあります。
あと、大玉トマトは水をやりすぎると甘さが薄くなっちゃうので、「乾かし気味に育てる」のがコツです。
表面の土が乾いて、指を入れてもサラッとしていたら水やりのタイミングですよ。
私も毎朝トマトに「おはよう!」って声かけながら水やりしてたら、ちゃんと育ってくれました♪
初心者におすすめの大玉トマト品種4選
初心者におすすめの大玉トマト品種4選を紹介します。
それぞれの品種について、詳しく見ていきましょう!
①「麗夏」:病気に強く育てやすい
「麗夏(れいか)」は、とにかく病気に強くて、初心者でも育てやすいことで人気の品種です。
特に「青枯病」「萎凋病」「葉カビ病」など、トマトがかかりやすい病気への耐性がしっかりしていて、安定して育ちます。
実の形もまん丸で、1個あたり200〜250gと大玉サイズなのに割れにくいのが嬉しいポイントです。
果肉はしっかりしていて、水分が少なめなので料理にも使いやすく、サンドイッチや煮込みにもピッタリなんですよ〜!
ホームセンターでもよく見かけるので、手に入りやすさも魅力ですね。
②「桃太郎」:味も見た目も優秀
言わずと知れた定番中の定番、「桃太郎」は大玉トマトの代表格です。
甘みと酸味のバランスがよく、生食用として人気が高く、サラダにぴったりの品種なんですよね。
果皮がややかたくて割れにくく、収穫してからもしっかり日持ちするので、ご近所へのおすそ分けにも◎。
育て方もシンプルで、初心者でも扱いやすいので「最初の一株は桃太郎!」って人も多いです。
実がしっかりと熟すと、鮮やかな赤になって収穫タイミングもわかりやすいので、家庭菜園デビューにもおすすめですよ~!
③「ホーム桃太郎」:家庭菜園の定番
「ホーム桃太郎」は、桃太郎シリーズの中でも家庭菜園向けに改良されたタイプです。
育てやすさがさらに強化されていて、初心者でも安心して育てられる品種として人気です。
果実はやや小ぶりですが、そのぶん早く実がつくのが特徴で、育てている楽しさをすぐに味わえるのがいいんですよね。
家庭の小さなスペースでもしっかり育ち、病気にも比較的強いので、プランターでもOK。
手軽にトマト栽培を始めたい方には、まずこの品種を選んでみてほしいですね。
④「ぜいたくトマト」:甘みが強くジューシー
ちょっと珍しいけど、味重視で選びたい人におすすめなのが「ぜいたくトマト」です。
名前のとおり、糖度が高くてとっても甘いのが特徴で、まるでフルーツトマトのようなジューシーさがあります。
トマトの青臭さが苦手な人でも「これなら食べられる!」ってなるくらい、食味がまろやかなんですよ~。
少しデリケートなので水やりや日当たりには気を使いますが、手間をかけるほど美味しさで返してくれます。
おいしさ重視で選びたい方は、ぜひ一度試してみてくださいね。
大玉トマトを育てる手順6ステップ
大玉トマトを育てる手順6ステップを分かりやすく解説します。
それでは、ひとつずつステップごとに見ていきましょう!
①苗選びと植え付け時期を確認
まずは苗選びと植え付けの時期をしっかり確認しましょう。
植え付けの適期は、地域によって差はあるものの、だいたい4月中旬〜5月上旬が目安です。
気温が安定して15℃以上になってからでないと、苗がストレスを受けてうまく育たないことが多いんです。
苗は「接ぎ木苗」や「病気に強い品種」など、育てやすさを優先して選びましょう。
あと、売り場に並んでいる苗でも成長度合いが違うので、葉の色や茎の太さをしっかりチェックしてくださいね!
②植える前に土づくりをしよう
トマトの出来を左右するのが、実は「土づくり」だったりします。
プランターなら市販の野菜用培養土を使えばOKですが、地植えなら「苦土石灰」でpHを調整して、完熟たい肥や堆肥を混ぜて1~2週間寝かせておくのが理想です。
土壌の酸性度を調整することで、トマトの根がしっかり伸びる環境が整います。
耕す深さは、少なくとも30cm以上、しっかりと空気が入るようにふかふかにしておくのがポイントです。
私も昔、土づくりをサボったせいで根腐れしたことがあるので…手間はかけたほうが結果的にラクですよ~!
③苗を植えたらすぐに支柱を立てる
植え付けが終わったら、すぐに支柱を立てましょう。
あとから立てようとすると、根を傷つけてしまうリスクがあるので、苗と一緒に立てるのが基本です。
支柱の長さは180cm以上がおすすめで、風で倒れないように地中に30cm以上差し込んでおくと安心です。
茎をヒモで支柱に結ぶときは「8の字」にして、茎に負担がかからないようにしましょう。
ぐらつきや倒伏を防ぐことで、後半の成長がグッと安定しますよ。
④雨よけ対策で病気予防
大玉トマトは特に「雨に弱い」作物なので、雨よけをしてあげると成功率がグンと上がります。
梅雨の時期になると、土の跳ね返りで「葉カビ病」や「疫病」にかかりやすくなるんですよね。
ビニール傘を逆さにして支柱にかぶせたり、園芸用の簡易ビニールトンネルを使うのが定番の方法です。
地面に敷く「マルチング」も、雨の跳ね返りを防ぐのにとても効果的です。
ちょっとしたひと手間で、病気のリスクを大きく減らせるので、ぜひ雨よけ対策をしてあげてくださいね!
⑤追肥と水管理でしっかり育てる
トマトは生育にあわせて「追肥」が必要です。
植え付けから2週間後くらいを目安に、化成肥料を少量ずつ、株元から少し離した場所にまいていきます。
肥料が多すぎると、葉ばかり茂って実がつかない「つるボケ」になることもあるので注意してください。
水やりは、土が乾いたときに朝たっぷりとが基本で、毎日ではなく、メリハリをつけるのが甘さアップの秘訣です。
雨の日や曇りの日は控えめに、晴れた日の翌朝などに調整してあげるといいですよ。
⑥収穫タイミングは完熟のサインで
実がしっかりと赤く色づいて、ヘタの周りまで赤くなってきたら収穫の合図です。
大玉トマトは、少し早めに採ると酸味が強く、完熟させると甘みがグッと増してくるんです。
品種によって収穫のタイミングは微妙に違いますが、全体が真っ赤になって、実が少しやわらかく感じたらベストタイミングです。
手で優しくひねってもぎ取るか、ハサミで切って収穫してください。
収穫したトマトは常温で保存すると甘さが引き立つので、冷蔵庫に入れすぎないようにしてくださいね!
大玉トマト栽培でやりがちな失敗5つと対策
大玉トマト栽培でやりがちな失敗5つと対策について紹介します。
初心者がやりがちなミスを知っておくと、グッと成功率が上がりますよ!
①水をやりすぎて根腐れ
一番よくある失敗が「水のあげすぎ」です。
トマトは乾燥ぎみに育てるのがコツなので、毎日たっぷりあげるのは逆効果になっちゃいます。
特に梅雨時期や曇りが続いた時期は、水が土に残りやすく、根っこが酸欠状態に陥って根腐れの原因になります。
水やりの目安は「土の表面が白っぽく乾いたとき」で、指を入れても乾いてるか確認するとベストです。
過保護にならず、少し放っておくくらいがちょうどいいんですよ〜!
②わき芽を放置して茎が混雑
わき芽って、気づいたらすごい勢いで伸びてるんですよね。
放っておくと主茎がどれかわからなくなるくらい混雑して、栄養が分散してしまいます。
すると実が小さくなったり、全体的にひょろひょろしてきたりと悪影響だらけ。
週に1回は株全体を見回して、わき芽が出ていないかチェックしましょう。
わき芽は小さいうちに手でつまんで取り除けばOK。育ちきってから切ると株に負担がかかるので注意ですよ!
③支柱が弱く倒れてしまう
「支柱は適当でいいか〜」と思ってると、あとで泣くことになります…!
特に大玉トマトは重みで倒れやすく、支柱が短かったり、固定が甘かったりすると、風でバタンと倒れちゃうんですよね。
支柱は180cm以上のものを選び、30〜40cmは地面にしっかり差し込むのがポイント。
さらに支柱を数本組み合わせて「合掌式」や「十字型」にすると、風に強くなって安心感もアップします。
しっかり支えてあげることで、実もたくさんつきやすくなりますよ~!
④肥料を与えすぎて実がならない
「たくさん実ってほしいから肥料をドバーッ!」ってやりたくなる気持ち、すっごくわかります。
でも実は、肥料のあげすぎもNGなんです。
葉ばかりがモサモサ茂って実がつかない「つるボケ」っていう状態になりやすいんですよね。
肥料は「少量をこまめに」が鉄則で、基本的には2〜3週間に1回、株元から少し離して与えるのがちょうどいいです。
初心者は、ゆっくり効く「緩効性肥料」からスタートするのが安心ですよ!
⑤病気や害虫を放置してしまう
トマトは病気にかかりやすい作物でもあります。
葉に白い粉がついたようになる「うどんこ病」や、実に斑点が出る「灰色かび病」など、よくある病気は早めの対処がカギです。
また、アブラムシやヨトウムシなどの害虫も発見が遅れると、あっという間に食い荒らされてしまいます。
週に1〜2回は株全体を観察して、葉の裏や実の近くをしっかり見ておきましょう。
少しでも異変を見つけたら、すぐに薬剤で対応するか、被害部分を切り取ることで被害を最小限にできますよ!
病害虫対策とトラブル回避のコツ
病害虫対策とトラブル回避のコツについてまとめました。
トマトを元気に育てるためには、日々の予防と観察がめちゃくちゃ大事なんです!
①うどんこ病・青枯病の予防方法
大玉トマトを育てるときに、特に気をつけたいのが「うどんこ病」と「青枯病」です。
うどんこ病は、葉っぱに白い粉がついたような症状が出て、光合成がうまくできなくなっちゃうんですよね。
青枯病はもっと厄介で、元気だった株が急にしおれて、文字通り“青いうちに枯れる”という恐ろしい病気です。
これらを防ぐためには、まず「風通しをよくする」「葉が混雑しないようにする」ことが大切です。
さらに、雨よけやマルチングで泥の跳ね返りを防ぐことで、病原菌の侵入もぐっと減らせます。
②害虫(アブラムシ・ヨトウムシ)の対策
トマトにはいろんな虫が寄ってきますが、特にやっかいなのが「アブラムシ」と「ヨトウムシ」です。
アブラムシは新芽や若い葉にびっしりついて、汁を吸って弱らせるだけでなく、ウイルス病の媒介もします。
ヨトウムシは夜のうちに活動して、朝になると葉や実がボロボロになってる…なんてことも。
これらの害虫には、見つけ次第すぐに捕殺するのが基本ですが、市販の殺虫剤(できれば自然由来のもの)を使うのも効果的です。
また、アブラムシは銀色の反射シートや黄色の粘着シートで予防できるので、プランターの周りに設置しておくと安心ですよ!
③プランターでもしっかり風通しを確保
「プランターだから狭いし、風通しは無理かな…」と思ってませんか?実はちょっとした工夫で改善できるんです。
まずは株間をしっかり空けることが大切で、最低でも30cm、できれば40cmほど空けて植えましょう。
また、周りに鉢や物がたくさん置いてあると風が抜けにくくなるので、余計なものは整理して風の通り道を作ってあげてください。
風通しが悪いと湿気がたまり、病気や虫の温床になっちゃいますからね。
たとえベランダでも、空気が回るように意識するだけで、ぐっと健康な株に育ちますよ!
④病気が出たときの処置方法
「あ、病気かも…?」と気づいたときのスピード対応が命です!
まず、異常のある葉や実を見つけたら、ためらわずに切り取って処分しましょう。
病気の部分を残すと、他の部分にどんどん広がっていきますからね。
薬剤を使う場合は、発病初期に対応できれば効果が高いので、病気が広がる前に散布するのがポイントです。
そして、病気の出た株はなるべく他の株から隔離して育てるようにすると、被害を最小限に抑えられます。
私も最初は戸惑いましたが、「早期発見・早期除去」を心がけておけば、なんとかなりますよ~!
大玉トマト栽培がもっと楽しくなる工夫3つ
大玉トマト栽培がもっと楽しくなる工夫3つを紹介します。
せっかく育てるなら、もっと楽しく、思い出にも残るような工夫をしてみませんか?
①子どもと一緒に育てて観察
家庭菜園って、子どもにとって最高の「生きた教材」なんですよね。
トマトが発芽して、花が咲いて、実ができて、赤く色づくまでの過程って、本当に感動的です。
毎日水やりを一緒にしたり、芽が出た!って大喜びしたり、収穫の瞬間なんてまるで宝探しみたいなワクワク感があります。
「今日は何個なったかな?」なんて一緒に数えたり、理科の観察日記にもピッタリですよ。
親子の会話も自然と増えるし、命の大切さや自然の不思議にも触れられる…もう育てない理由ないですよね!
②収穫したら料理で楽しむ
トマトって、育てたあとがまた楽しいんです。
収穫したばかりのトマトを使って、サラダにしたり、パスタソースにしたり…おうちごはんが一気にグレードアップします!
朝採れトマトは、市販のトマトとは比べものにならないほど甘くてジューシーなんですよ。
ミネストローネにすると、トマトのうま味が溶け出して、野菜嫌いの子どももペロリと食べちゃうほど。
自分で育てたトマトで家族の食卓を彩れるって、本当に嬉しいし、育てるモチベーションにもなりますよ~!
③SNSに育成記録を投稿してみる
最近は、家庭菜園の様子をSNSに記録している人も増えてますよね。
InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどで「#家庭菜園」「#トマト栽培」って検索すると、同じように育ててる仲間がいっぱい見つかります。
写真を撮って「今日はこんなに大きくなったよ!」とか、「初めて花が咲いた!」って投稿するだけで、めちゃくちゃ反応があったりするんです。
自分だけの成長記録として残るのはもちろん、同じ趣味の人とつながれるのも楽しいポイント。
私も初めてのときに投稿した写真に「きれいに育ってますね!」ってコメントがきて、すごく励みになったのを覚えてます!
まとめ|大玉トマトの育て方 初心者でも楽しめるコツ
大玉トマトは、ちょっと手間がかかる分だけ、実ったときの感動も大きい野菜です。
初心者の方でも、基本さえ押さえればしっかり育てることができますし、親子での観察や料理、SNS投稿など楽しみ方もたくさんあります。
今回ご紹介したコツを活かして、自分だけの美味しいトマトを育ててみてくださいね。