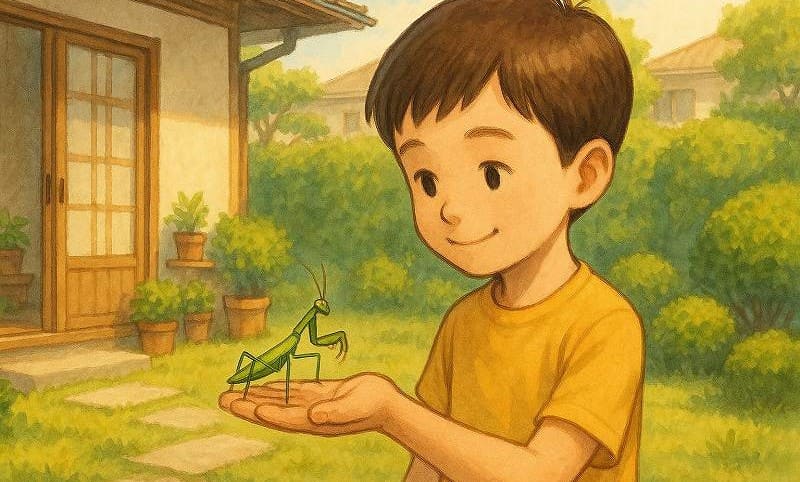カマキリの正しい持ち方を知っていますか?
この記事では、カマキリと安全にふれあうためのコツや、「かまきりリレー」と呼ばれる楽しい遊び方まで、やさしくわかりやすく解説していきます。
実は、カマキリはそっと手に乗せれば、まったく攻撃してこない優しい虫なんです。
怖がらずに自然と仲良くなる第一歩として、ぜひ読んでみてくださいね。
子どもと一緒に安心して楽しめる内容なので、虫がちょっと苦手な方にもおすすめです。
カマキリ持ち方の正解は?安全に触れるコツ7つ
カマキリ持ち方の正解は?安全に触れるコツ7つについて解説します。
- ①カマキリはなぜ怖がられるのか
- ②攻撃される理由は「びっくりさせる」から
- ③まずは葉っぱの上に乗せてみよう
- ④そっと手に乗せれば安全
- ⑤暴れたらどうする?注意点もチェック
- ⑥飛ぶのはオスだけ?驚かないために知っておこう
- ⑦ごきげんなカマキリは暴れない
それでは、それぞれのポイントを詳しく解説していきますね。
①カマキリはなぜ怖がられるのか
カマキリって、見た目がとにかくインパクトありますよね。
鋭いカマに、大きな目、そして他の虫をバリバリ食べる姿…。この姿に「かっこいい!」と思う子もいれば、「こわい…」と感じる子もいるんです。
実は、人気の理由も怖がられる理由も、どちらもカマキリの「たくましさ」から来ています。
子どもたちは本能的に、「強いもの」に惹かれたり、怖がったりしますよね。
だからこそ、まずはカマキリに対して「正しく理解すること」が大切なんです。
②攻撃される理由は「びっくりさせる」から
カマキリが攻撃してくるとき、それは「敵から身を守ろうとしている時」です。
急に掴まれたり、予想外の動きをされたとき、カマキリはのけぞって暴れたり、カマで引っかいたりするんです。
これは、「恐ろしい手から逃げたい!」という必死の行動。
つまり、「こちらが脅かさなければ、攻撃してくることはほぼない」んですよ。
カマキリを触るときは、「驚かせない」「ゆっくり近づく」がポイントになります。
③まずは葉っぱの上に乗せてみよう
最初から手で触ろうとすると、やっぱりカマキリも警戒します。
だから、「葉っぱの上に乗せてから、手に移す」のがベスト。
虫アミで捕まえたときも、いきなり手に乗せるのではなく、いったん落ち着かせてから。
葉っぱごとそっと手に近づけると、カマキリも安心して動いてくれます。
この方法なら、初心者でも安全にカマキリとふれあえますよ。
④そっと手に乗せれば安全
実は、カマキリって「そーっと手に乗せれば、すごくおとなしい」んです。
跳ねたり飛びついたりはしません。ぴょんぴょんするのはバッタのイメージですね。
手の上では、ゆっくり歩くだけ。びっくりするような動きはほとんどありません。
だから、無理に掴もうとせず「乗ってもらう」感覚で接しましょう。
カマキリさんも、「あ、この人は安全だな」と思えば、ごきげんでいてくれます。
⑤暴れたらどうする?注意点もチェック
どれだけ優しくしても、カマキリが急にパニックになることはあります。
そんなときは、まず手を引っ込めたりせず、落ち着いて様子を見てあげましょう。
急に動いたり、叫んだりすると、カマキリもさらにビックリします。
もし手から落ちてしまったら、焦らずそっと拾ってあげればOKです。
大切なのは「冷静さ」と「やさしさ」。虫とのふれあいって、思いやりが大事なんですよね。
⑥飛ぶのはオスだけ?驚かないために知っておこう
実は、オスのカマキリは身軽で「パタパタと飛ぶこと」があります。
メスに比べて体が軽く、翅(はね)を使って逃げる能力が高いんです。
手に乗っているときも、「びっくりして飛んでいく」ことがあります。
この行動は、「危険を感じたサイン」。無理に追いかけたりせず、そっとしておいてあげてください。
オスとメスの違いを知っておくと、さらに安全に接することができますよ。
⑦ごきげんなカマキリは暴れない
カマキリが落ち着いているときは、引っかいたり噛みついたりしません。
たとえば、記事で紹介されていた丹波の森公苑では、葉っぱの上から帽子の上までのんびり歩いていったカマキリがいたそうです。
そんな「ごきげんモード」のときは、まるでペットのように穏やかなんです。
この状態にしてあげるには、やっぱり「最初のふれあい」が大切。
怖がらせずに、安心させてあげること。それが、カマキリとの仲良しの秘訣です。
カマキリリレーってなに?やってみたい遊び方5ステップ
カマキリリレーってなに?やってみたい遊び方5ステップについて解説します。
それでは、カマキリリレーのやり方と魅力を順番に見ていきましょう。
①手のひらで歩かせるのが第一歩
カマキリリレーの始まりは、まず「カマキリを手のひらの上で歩かせる」ところからです。
最初にそっと手を差し出して、すでに紹介したように、カマキリを乗せます。
このとき、無理に誘導したり掴んだりせず、「自分から歩き出す」のを待ちましょう。
カマキリが安心していれば、自然とゆっくり歩き出します。
この「信頼関係」こそが、リレーのカギなんです。
②もう片方の手を前に出すと自然に移動
カマキリが手のひらを歩き始めたら、次にするのは「もう片方の手を前に差し出す」こと。
すると、カマキリはそのまま前へ進もうとして、自然と新しい手に移ってくれます。
この動きがとてもおもしろくて、子どもたちも夢中になるポイントです。
カマキリにとっても、前に道があれば進みたくなる習性を活かしているんですね。
まさに、生きものの自然な動きを大切にしたふれあい方です。
③お友だちの手にリレーしてみよう
両手でのリレーに慣れてきたら、今度は「お友だちの手にリレー」してみましょう。
自分の手の前に、となりの人が手を出してくれたら、カマキリはそのまま歩いていきます。
この遊びが「かまきりリレー」と呼ばれるゆえんです。
1人だけでなく、数人でつないでいくと、まるで「バトンを渡す」ような感覚になります。
この自然体験が、子どもたちにとって特別な思い出になるはずです。
④子どものカマキリで練習がおすすめ
カマキリリレーをはじめてやるときは、「子どものカマキリ」での練習がおすすめです。
初夏に見かける、まだ小さくて軽いカマキリなら、驚かせてしまうリスクも少なくなります。
また、小さいぶん飛ぶ力も弱く、ゆっくりした動きが多いので安心です。
最初は手のひらでじっくり観察するだけでも十分。
「慣れてきたな」と思ったら、リレーにチャレンジしてみましょう。
⑤カマキリリレーが教えてくれること
カマキリリレーは、ただの遊びではありません。
虫とどう接すればいいか、どうすれば安心してもらえるか――それを自然と学べる体験なんです。
「生きものには、やさしくすることが大事」という気づきが、遊びの中に込められています。
それに、自分がリレーをうまくつなげたときの達成感や、「やったね!」と笑い合う楽しさも魅力です。
虫が好きになるきっかけにもなるし、苦手意識のある子でも「触れてみようかな」と思えるチャンスになりますよ。
カマキリが怒らない持ち方3選(上級者向け)
カマキリが怒らない持ち方3選(上級者向け)について解説します。
ちょっと難しいけど、正しくやれば安全。そんな持ち方を紹介しますね。
①翅(はね)をつかむ方法
カマキリの翅(はね)を持つ方法は、最も安全に見えるかもしれません。
というのも、翅を持つと、あの鋭いカマが届かない位置で固定できるからです。
しかし注意が必要なのは、「翅を掴もうとするまでに暴れることが多い」点。
カマキリ自身は、翅を開いたり閉じたりすることはありますが、自分から差し出すことはありません。
だから、無理に後ろからつかもうとすると、「何だなんだ!」と驚いてしまい、激しくのけぞって抵抗することがあります。
それでも翅をしっかりと両側から優しく包み込むように掴めば、安定した状態で持つことができます。
ただしこの方法は、急に掴まれるとびっくりするので、カマキリが落ち着いているときを見計らってくださいね。
②背中をそっとつかむ方法
もうひとつの持ち方が、背中をつかむ方法です。
このときのポイントは、「下の方を持つ」こと。できるだけカマに近づかないように持つのがコツです。
とはいえ、この持ち方も簡単ではありません。
カマキリは、「何かが背中に近づいてきた」と感じると、すぐに身構えます。
なので、持つときは素早く、でも力を入れすぎず、やさしく背中を包み込むようにしましょう。
一度つかめば、体を固定できるので移動させるときなどに便利ですが、最初の一手が難関です。
この方法は経験者向けですが、子どもと一緒に観察する大人が使う分には、知っておいて損はありませんよ。
③どの方法も「驚かせない」が大前提
どんな持ち方であっても、カマキリを驚かせたら意味がありません。
すべての基本は「やさしく、そっと、落ち着いて」です。
いきなり触ろうとしたり、大声を出したりすると、それだけで暴れ出してしまいます。
虫も生きもの。恐怖を感じたら、命を守ろうとします。
それは当然のことですよね。
だからこそ、「虫に好かれる持ち方」という視点が大事なんです。
安全に持つテクニックも大事ですが、それ以上に大切なのは「相手を思いやる気持ち」です。
この気持ちがあれば、どんな方法もきっと上手にできるようになりますよ。
虫が苦手な子どもでもカマキリと仲良くなれる方法
虫が苦手な子どもでもカマキリと仲良くなれる方法について解説します。
虫が苦手な子どもでも、やさしく一歩ずつ進めば、カマキリと仲良くなれますよ。
①怖がらないコツを教えてあげよう
カマキリが「こわい」と思われる理由の多くは、その見た目や動きにあります。
特に小さな子にとって、急に動く虫はびっくりする存在ですよね。
そんなときは、「カマキリはこわくないよ」ではなく、「こうすると安心だよ」と伝えてあげましょう。
たとえば、「そーっと手を出すと、カマキリもこわがらないんだよ」と教えることで、虫も人も同じように怖がることがあるんだと理解できるようになります。
怖がる気持ちを否定せず、「どうすればうまくいくか」を一緒に考えるのがポイントです。
②まずは見るだけでもOK
いきなり触る必要はありません。
まずは虫かごの中のカマキリを観察したり、葉っぱの上でじっとしている姿を見るだけで十分です。
ガラスやネット越しでも、動きや顔つきを見ることができるので、「興味」や「慣れ」を育てるにはとてもいいステップになります。
そのうち、「こわいけど、おもしろいかも…」という気持ちが芽生えてきますよ。
観察図鑑を使って、「このカマキリは○○カマキリかな?」とクイズ形式で楽しむのもおすすめです。
③触れるようになるまでのステップ
触れるようになるには、段階を踏むのが一番の近道です。
たとえば、こんなステップが効果的です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ1 | 図鑑や写真で見る |
| ステップ2 | 虫かごの中で観察する |
| ステップ3 | 網や葉っぱの上から見る |
| ステップ4 | 葉っぱごと手に乗せてみる |
| ステップ5 | そっと手に乗せてみる |
この順番なら、無理せずに徐々に慣れていくことができます。
「急がなくていいよ」と声をかけてあげることが、自信につながるんですよ。
④自然とのふれあいは大きな成長に
虫が苦手な子が、カマキリと仲良くなれるようになると、それだけで大きな成長です。
「怖いけど、やってみた」「できた!」「すごいね!」という体験が、自信や好奇心を育てます。
また、カマキリとじっくりふれあうことで、「生きものにやさしくする心」も自然と育まれます。
虫とのふれあいは、自然と向き合う力、他者を思いやる気持ち、集中力など、たくさんの力につながっています。
この経験は、教科書では学べない「大切な学び」になるんです。
まとめ|カマキリ持ち方のポイントを振り返ろう
| カマキリ持ち方のコツ7つ |
|---|
| ①カマキリはなぜ怖がられるのか |
| ②攻撃される理由は「びっくりさせる」から |
| ③まずは葉っぱの上に乗せてみよう |
| ④そっと手に乗せれば安全 |
| ⑤暴れたらどうする?注意点もチェック |
| ⑥飛ぶのはオスだけ?驚かないために知っておこう |
| ⑦ごきげんなカマキリは暴れない |
カマキリの持ち方には、ちょっとした「コツ」と「思いやり」が必要です。
無理に掴んだりせず、相手がびっくりしないように、そっと接することで、カマキリも安心してくれます。
特に「葉っぱに乗せてから手に移す」「ゆっくりと手を出す」など、自然な流れで行うことが大切でしたね。
さらに、「かまきりリレー」のような遊びを通じて、楽しみながらふれあうことができれば、子どもたちにとっても良い経験になります。
虫が苦手な子でも、少しずつ慣れていけば、自然との関わりをポジティブに変えていけるはずです。
カマキリを通じて、命を大切にする気持ちや、他者を思いやる優しさが育まれること。それこそが、自然とふれあう意味かもしれません。