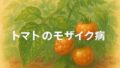さつまいも害虫は、葉や茎を食害するものと、収穫対象である根(塊根)を加害するものに分かれます。
葉を狙う害虫は光合成を妨げ、生育を阻害し、根を食害する害虫は収量や品質を直接的に下げてしまいます。
代表的な害虫には、ナカジロシタバやヨトウムシ類などの食葉性幼虫、コナジラミやアブラムシといった吸汁性害虫、さらにコガネムシ類やセンチュウ、ゾウムシ類といった根を狙うものがいます。
被害は「葉の穴あき」「退色」「塊根の食害痕や腐敗」といった症状で見分けることができます。
防除には、防虫ネットや雑草管理、土壌消毒などの予防策が有効であり、発生初期を狙った薬剤散布が効果的です。
特にサツマイモノメイガ、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシは「特殊病害虫」に指定され、発生地域からの苗や塊根の移動が法律で制限されています。
この記事では、サツマイモの害虫被害の症状、原因となる主な害虫、そして実際に役立つ対策を詳しく解説していきます。
さつまいも害虫の主な症状と見分け方
さつまいも害虫の主な症状と見分け方について解説します。
それでは、具体的に説明していきますね。
①葉の穴あきや白い筋状の痕
葉に現れる害虫被害の典型的な症状は「穴あき」と「白い筋状の痕」です。
ナカジロシタバやヨトウムシ類の幼虫は、若い葉の裏側から表皮を残して食害するため、葉が白く透けて見える状態になります。
成長した幼虫はさらに大胆に食べ進め、大きな穴を開けながら葉を食い荒らします。葉の骨組みだけが残ることもあり、光合成能力を著しく下げてしまいます。
また、ヒルガオハモグリガなどの幼虫は葉の内部を食べ進むため、白い線が走るような特徴的な痕を残します。
多発すると葉全体が赤茶色に変わり、まるで火に焼けたように見えることもあります。このような症状は、発生初期に気づくことが防除成功のカギになります。
被害を見つけたら、被害葉を確認し、場合によっては早急に捕殺や薬剤散布を行う必要があります。特に苗を育てている段階で症状が出た場合は、株全体の成長に直結するため注意が必要です。
②葉の巻き込みや萎れ
葉が丸まったり、くるっと巻き込んだりしている場合は、イモキバガやアブラムシ類の被害が疑われます。
イモキバガの幼虫は葉を巻いたり折り曲げたりして中に潜み、葉の内側を食べるため、外から見ても中身が透けて白っぽくなります。さらに時間が経つと枯れたように褐色化していきます。
アブラムシ類の吸汁被害では、葉の形が不自然に縮れたり、丸まったりすることが特徴です。ウイルス病を媒介することもあり、単なる害虫被害にとどまらない深刻なリスクを伴います。
葉の巻き込みは単なる乾燥や病気と間違えやすいため、裏側をチェックすることが大切です。
こうした症状を早く発見するためには、日常的な観察と、葉を手にとって裏まで確認する習慣が役立ちます。
③塊根のえぐれや黒変
収穫の楽しみを奪う深刻な被害が「塊根のえぐれ」や「黒変」です。
コガネムシ類の幼虫は根の表面を削るように食害し、ガサガサとした傷を残します。表面がひどく傷つくと見た目が悪くなり、市場価値が下がります。
さらに被害が進むと、コメツキムシ類(ハリガネムシ)が塊根内部に穴を開け、針で刺したような丸い痕を残します。
内部に入り込んだ場合は腐敗を引き起こすこともあります。ゾウムシ類の被害では内部が黒く変色し、異臭や苦みが出て食用に適さなくなります。
このような塊根被害は、収穫期まで気づきにくいのが厄介です。掘り上げてから初めて被害が分かることも多いため、予防的な管理が非常に重要です。
④株全体の生育不良
葉や茎、根の被害が重なると、株全体が弱り、成長不良を引き起こします。例えばカメムシ類が茎や新梢から吸汁すると、株全体がしおれたように見えることがあります。
コナジラミやアブラムシの媒介によってウイルス病に感染した場合も、葉の変形や黄化が進み、収穫量が大きく落ちてしまいます。
生育不良は複数の害虫や病気が同時に関与しているケースが多いため、症状を一つずつ切り分けて考えることが大切です。
「萎れている=水不足」と思い込まず、害虫の可能性も必ず疑うことが、早期対策につながります。
さつまいも害虫が発生する原因と種類
さつまいも害虫が発生する原因と種類について解説します。
それぞれの原因と代表的な種類について、詳しく見ていきましょう。
①食葉性害虫(ナカジロシタバ・ヨトウムシ類)
食葉性害虫は、文字通り「葉を食べる害虫」で、サツマイモ栽培において最も目に見えやすい被害を与えます。代表的な種類はナカジロシタバやヨトウムシ類です。
ナカジロシタバは幼虫の時期に若葉やつる先をかじり、成長すると葉を骨組みだけにするほど食べ尽くします。
ヨトウムシ類は夜行性で、日中は土の中に潜み、夜になると活動して葉を食い荒らす習性があります。そのため、昼間は被害に気づきにくく、夜間の観察が発生確認には有効です。
これらの害虫は、葉に大きな穴を残し、光合成を妨げて株全体の活力を奪います。発生要因としては、圃場の周囲に雑草が多い場合や、気温が高く湿度がある条件が挙げられます。
特に梅雨明けから夏にかけて発生が増える傾向があります。
②吸汁性害虫(コナジラミ・アブラムシ類)
吸汁性害虫は、葉や茎に口針を刺して植物の汁を吸うタイプの害虫です。サツマイモで問題になるのは、コナジラミやアブラムシ類です。
コナジラミ類は葉裏に寄生して栄養分を吸い取るため、葉が黄変してしおれやすくなります。さらに、排泄物によってすす病を誘発したり、葉巻ウイルスを媒介したりする点が大きな問題です。
アブラムシ類も同様に汁を吸いますが、葉を縮れさせ、成長点を損なうことで株全体の成長に影響を与えます。
これらの害虫は繁殖力が非常に高く、短期間で数を増やすのが特徴です。気温が温暖で雨が少ない環境では爆発的に増加することがあり、予防的な管理が重要です。
③塊根を食害する害虫(コガネムシ・センチュウ)
サツマイモの収穫物である塊根を直接加害するのが、コガネムシ類やセンチュウ類です。コガネムシの幼虫は土中で過ごし、根の表面を削るように食べるため、ガサガサした食害痕が残ります。
被害が進むと見た目が悪くなるだけでなく、二次感染による腐敗も起こります。
センチュウ類は顕微鏡サイズの線虫で、根にコブを作ったり、褐色の斑点を形成したりします。生育初期に感染すると、根が大きくならず、収穫量が大幅に減少することもあります。
特にネコブセンチュウやネグサレセンチュウは要注意害虫とされています。
これらは土壌環境に大きく左右されるため、連作を避けたり、土壌消毒を行ったりすることが効果的な防除策となります。
④特殊病害虫(サツマイモノメイガ・ゾウムシ類)
サツマイモ害虫の中でも特に厄介で、法律で規制されているのが「特殊病害虫」です。代表的なものがサツマイモノメイガ、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシです。
サツマイモノメイガは葉や茎の内部に食入し、内部を黒変させる特徴があります。
ゾウムシ類は塊根内部に潜り込むため、見た目では気づきにくく、収穫してから被害が判明することが多いのが特徴です。
食害されたサツマイモは異臭や苦みがあり、食用や飼料用として使えなくなります。
これらの害虫は植物防疫法に基づき、発生地域から苗や芋の移動が制限されています。
そのため、発生予察情報に注意し、地域ごとの防除体制に従うことが必須です。
葉や茎を食害する害虫への対策5つ
葉や茎を食害する害虫への対策5つについて解説します。
それぞれのポイントを具体的に解説しますね。
①発生初期の薬剤散布
食葉性害虫や吸汁性害虫に共通して効果的なのが「発生初期の薬剤散布」です。
ナカジロシタバやスズメガ類などの幼虫は、成長すると摂食量が一気に増え、葉を数日で食い尽くしてしまうほどです。
そのため、若齢幼虫の段階で薬剤を散布することが被害を最小限に抑えるカギとなります。
発生初期を見極めるためには、葉先や若い芽の部分を観察するのが有効です。
卵や小さな糞を見つけた時点で、早めに対応することが重要です。薬剤は適用作物と害虫に登録されたものを使い、使用回数や希釈倍率を必ず守りましょう。
②防虫ネットの利用
防虫ネットは、物理的に害虫の侵入を防ぐシンプルかつ効果的な手段です。特にコナジラミやアブラムシのような飛来性害虫には有効で、定植直後に被覆することで被害を大きく減らせます。
目合い1mm以下のネットを使えば、サツマイモトビハムシなどの小さな害虫の侵入も防止可能です。
ただし、防虫ネットの隙間から入り込まれると中で繁殖してしまうため、設置時は地面にしっかり固定し、破れがないかを確認することが大切です。
風通しが悪くならないように工夫することも長期的な使用には欠かせません。
③特徴的な被害葉の捕殺
イモキバガやヒルガオハモグリガのように、葉を巻いたり内部に潜り込んだりする害虫には「捕殺」が有効です。
葉が不自然に丸まっていたり、白く透けて見えたりする場合は、中を開いて幼虫を取り除きます。この作業は地道ですが、被害拡大を抑えるのに非常に役立ちます。
特に家庭菜園規模では、農薬散布を控えたい場合もあるため、捕殺は安全で確実な防除方法といえます。巻いた葉を見逃さず、こまめに点検する習慣が重要です。
④雑草管理による侵入防止
圃場周辺の雑草は、多くの害虫にとって格好の隠れ家や発生源となります。特にカメムシ類やアブラムシ類は雑草から飛来してサツマイモに移動するため、雑草管理は侵入防止の第一歩です。
畦間や畑の周囲を定期的に除草することで、害虫の住処を減らし、被害を軽減できます。雑草管理は病害虫全般に有効で、予防的な効果が非常に高い方法です。
⑤耐性を考慮した農薬ローテーション
アブラムシやコナジラミは繁殖力が高く、薬剤抵抗性がつきやすい害虫です。
そのため、同じ成分の農薬を繰り返し使うのではなく、複数の作用機構を持つ薬剤をローテーションで使用することが推奨されます。
また、薬剤だけに依存するのではなく、防虫ネットや雑草管理などの物理的・耕種的防除と組み合わせることで、持続的に効果を発揮できます。
統合的な害虫管理(IPM)の一環として、バランスの取れた対策を行うことが大切です。
塊根を食害する害虫への対策4つ
塊根を食害する害虫への対策4つについて解説します。
収穫物そのものである塊根を守るために、これらの対策は特に重要です。
①土壌消毒と連作回避
塊根に被害を与えるセンチュウ類は、土壌中に潜むため発見が難しく、予防的対策が欠かせません。代表的な方法が「土壌消毒」と「連作回避」です。
土壌消毒には、薬剤を使った化学的手法と、太陽熱を利用した物理的手法があります。
太陽熱消毒は透明ビニールで畑を覆い、夏場の強い日差しで地温を高めて害虫を死滅させる方法で、家庭菜園にも応用しやすい手段です。
連作は土壌害虫の密度を上げる原因となるため、サツマイモを同じ圃場で続けて栽培することは避けた方が良いでしょう。
異なる作物と輪作することで害虫の生息サイクルを断ち切り、被害を減らす効果が期待できます。
②定植前の薬剤防除
コガネムシ類やコメツキムシ類の幼虫は、土中で活動しながらサツマイモの塊根を狙います。これらは苗を植える前の段階で薬剤防除を行うのが効果的です。
特に被害が予想される圃場では、あらかじめ登録薬剤を土壌処理として使用することで、定植後のリスクを大幅に減らせます。
薬剤処理の際は、ラベルに記載された対象害虫と適用作物を必ず確認しましょう。使用できない薬剤を使うと効果が出ないだけでなく、サツマイモに悪影響を及ぼすことがあります。
③防虫網で成虫侵入を防ぐ
コガネムシやサツマイモトビハムシなどの成虫は、飛来して土中に産卵します。幼虫被害を防ぐには、成虫が畑に入り込むのを物理的に遮断するのが有効です。
目合い1mm以下の防虫網を畑全体に設置すれば、成虫の侵入と産卵を同時に防ぐことができます。
特に定植後の若い苗は食害されやすいため、初期生育を守るためにも防虫網は重要です。
ただし、網の隙間や端の管理が甘いと侵入されてしまうため、圃場をしっかり覆うことがポイントです。
④発生地域での苗や塊根の使用制限
アリモドキゾウムシやイモゾウムシは、塊根の内部に潜り込むため被害の発見が難しく、気づいたときには収穫物が使えない状態になっていることが多い害虫です。
これらは「特殊病害虫」に指定されており、発生地域では苗や芋の持ち出しが法律で禁止されています。
被害の拡散を防ぐためにも、発生が確認されている地域からの苗や塊根を使わないことが絶対条件です。
購入する場合は必ず信頼できる供給元から入手し、農林水産省や自治体が発表する発生情報を確認しておくことが必要です。
こうした法的な制限は、地域全体でサツマイモ栽培を守るための大切なルールです。農家だけでなく家庭菜園利用者も遵守することが求められます。
さつまいも害虫を防ぐ総合的な予防戦略
さつまいも害虫を防ぐ総合的な予防戦略について解説します。
これらの予防戦略を組み合わせることで、被害リスクを最小限に抑えることができます。
①圃場周辺の環境整備
圃場やその周辺の環境整備は、あらゆる害虫防除の基本です。雑草が多いと害虫の発生源や隠れ場所となり、カメムシやアブラムシ、ゾウムシ類の侵入を助長します。
そのため、圃場の周辺を定期的に除草し、不要な植物を取り除くことが欠かせません。
また、圃場周辺に堆肥や収穫残渣を放置すると害虫が繁殖する要因になります。収穫後は残さをしっかり処分し、清潔な環境を保つことが重要です。
こうした管理は病害虫全般の抑制にもつながります。
②太陽熱利用や物理的防除
土壌中のセンチュウやコガネムシ類幼虫を減らすには、太陽熱を利用した土壌消毒や、防虫ネットなどの物理的防除が効果的です。
太陽熱消毒は夏場に透明ビニールで畑を覆い、数週間かけて土壌温度を高める方法で、害虫や病原菌を減らす効果が期待できます。
防虫ネットは害虫の侵入や産卵を直接防ぐため、初期の被害を防ぐ上で特に有効です。目合いの細かいネットを使用し、圃場全体を覆うことが推奨されます。
これらは薬剤に頼らない持続可能な防除方法として注目されています。
③発生予察情報の活用
農林水産省や都道府県が発表する「発生予察情報」を活用することで、害虫防除を効率的に行えます。
予察情報では、特定の害虫の発生状況や今後の予測が提供されるため、農薬散布のタイミングや物理的防除の実施時期を決める参考になります。
特にサツマイモノメイガやゾウムシ類のように被害が深刻な害虫については、地域単位での監視体制が整えられており、発生地域の情報を知ることが予防の第一歩です。
個人栽培者も自治体の発表に注意を払い、適切に行動することが求められます。
④法律で定められた防疫措置の遵守
サツマイモノメイガ、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシの3種は「特殊病害虫」に指定されています。
これらは植物防疫法に基づき、発生地域から苗や塊根を移動させることが禁止されています。違反すると法律違反となり、地域全体に深刻な被害を及ぼす可能性があります。
そのため、発生地域で栽培する際は法的措置を守ることが不可欠です。また、苗や塊根を購入する際には産地を確認し、信頼できる供給元から入手することが大切です。
これは家庭菜園であっても例外ではなく、栽培者全員が責任を持って取り組むべき防除策です。
総合的な予防戦略は、一つの方法に依存するのではなく、物理的・耕種的・化学的手段を組み合わせて実施することがポイントです。
統合的害虫管理(IPM)の視点を持ち、継続的に畑を観察していくことが、安定した収穫につながります。
まとめ|さつまいも害虫を防ぐためにできること
さつまいも害虫は、葉や茎、そして収穫物である塊根に大きな被害を与えます。
葉では穴あきや白い筋状の痕、巻き込みや縮れなどが見られ、根ではえぐれや黒変が収穫後に判明するケースが多いです。
原因となる害虫は、ナカジロシタバやヨトウムシ類といった食葉性、コナジラミやアブラムシ類の吸汁性、さらにコガネムシやセンチュウ類、ゾウムシ類と多岐にわたります。
中でもサツマイモノメイガやイモゾウムシ類は「特殊病害虫」に指定され、発生地域からの苗や塊根の移動が禁止されています。
防除の基本は、発生初期を見逃さない観察と、薬剤・防虫ネット・雑草管理など複数の方法を組み合わせた総合的な管理です。
また、地域ごとの発生予察情報を活用し、法律に基づくルールを守ることが、被害を防ぐためには不可欠です。
安心して収穫を楽しむためには、日常的な点検と予防的対策が一番の近道です。
今日からできる小さな習慣が、収穫の喜びを守ってくれますよ。