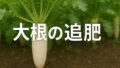ジャガイモの追肥の時期は「芽かきの後、開花前」がベストです。これを守ることで、イモの肥大を助け、収穫量をしっかり増やすことができます。
ジャガイモは肥料を与えなくても育つイメージがあるかもしれませんが、実際には適切な施肥が欠かせません。
元肥で土の基盤を整え、芽かき後に追肥をすることで、健全な株の成長と大きなイモの収穫が可能になります。
この記事では、ジャガイモ栽培に必要な肥料の種類や成分バランス、追肥のタイミングや注意点を徹底的に解説します。
どの肥料を使うべきか、与え方はどうすればいいのか、そして失敗しないためのチェックポイントもまとめました。
「追肥のタイミングがよくわからない」「肥料を与えすぎてしまいそうで不安」と感じている方も、この記事を読めば安心してジャガイモ栽培を楽しめますよ。
豊作の秘訣をつかんで、自分の畑やプランターで立派なジャガイモを育ててみてくださいね。
ジャガイモ追肥時期を見極めるコツ
ジャガイモ追肥時期を見極めるコツについて解説します。
それでは詳しく解説していきますね。
①芽かき後に与えるのが基本
ジャガイモの追肥は「芽かきの後」に行うのが基本です。
芽かきとは、種芋を植えてから1か月ほど経った頃に行う作業で、地上に伸びてきた芽が10cmほどになった時点で、強い芽だけを残して他を取り除きます。
この芽かきの直後が追肥のベストタイミングです。理由は、ここからイモが肥大を始めるからです。肥料を与えることで根から栄養がスムーズに行き渡り、芋の数や大きさがぐんとアップします。
追肥を与えるときは、株元から少し離れたところに肥料をまいて土となじませるようにしてください。直接株元に肥料を置くと、根が傷んだり肥料焼けを起こす原因になります。
また、芽かきと追肥を組み合わせることで、生育のリズムが整いやすくなり、健全な株に育ちます。追肥を忘れずに行うことで、収穫量の差が大きく出てくるので要注意です。
芽かきの後の追肥は、ジャガイモ栽培の成功に欠かせない作業です。しっかり意識して取り入れましょう。
②開花前に追肥を終える
ジャガイモの追肥は「開花前に終える」ことが鉄則です。開花してから追肥をしてしまうと、茎や葉の成長ばかりが促されてしまい、肝心の芋に栄養がいきません。
ジャガイモの開花は、植え付けからおよそ50〜60日後に始まります。その前に追肥を済ませておくことで、葉から芋へと栄養がしっかり移行し、大きなイモに育ちます。
もし追肥が遅れて開花後になってしまうと、茎葉の維持にエネルギーを使ってしまい、芋が小さく水っぽくなったり、奇形になってしまうリスクが高まります。
栽培全体の出来に大きな影響を与えるため注意が必要です。
つまり、追肥は「芽かき後から開花前まで」が黄金ルールです。これを守るだけで、ジャガイモの収穫量と品質が大きく変わってきます。
③土寄せとセットで行う
追肥のタイミングでは「土寄せ」とセットで行うのがポイントです。土寄せとは、株元に土を寄せて盛り上げる作業で、追肥と同時に行うと効率的です。
土寄せを行うことで、ジャガイモが地表に出て日光に当たるのを防ぎます。日光を浴びたジャガイモは緑化してしまい、ソラニンやチャコニンといった有害な成分が発生してしまいます。
また、土寄せをしっかり行うことで根がしっかり張り、倒伏しにくくなります。肥料の効果を根が十分に吸収できる環境づくりにもつながります。
追肥のときに土寄せをセットで行うことは、収穫量アップと品質維持の両面でとても大切です。必ず合わせて行うようにしましょう。
④追肥の量は控えめに調整
追肥を与えるときは「控えめ」に調整するのがコツです。肥料をたっぷり与えればよく育つと思われがちですが、ジャガイモに関しては逆効果になることがあります。
特に窒素が多すぎると、葉や茎ばかりが茂り、肝心の芋が小さくなってしまいます。さらに病気や害虫の被害を受けやすくなることもあるため注意が必要です。
追肥の目安量は、1株あたり一握り程度の固形肥料です。肥料袋に書かれている推奨量を確認し、守ることも大切です。肥料のやりすぎは収穫の失敗につながるので、適量を守りましょう。
また、肥料不足が見られた場合には、補助的に液体肥料を少量与えると良いです。即効性があるため、短期間で株に元気を取り戻させることができます。
追肥の量は「少し控えめ」を心がけるのが、豊作への秘訣です。
ジャガイモ栽培に必要な肥料の種類
ジャガイモ栽培に必要な肥料の種類について解説します。
それでは詳しく説明していきますね。
①固形肥料と液体肥料の違い
ジャガイモ栽培では、基本的に「固形肥料」をメインに使い、必要に応じて「液体肥料」を補助的に使うのがおすすめです。
固形肥料は、土の中でゆっくりと効いていく特徴があります。そのため、長期間にわたって安定して栄養を供給できるのがメリットです。元肥として使えば、ジャガイモの初期成長をしっかりサポートしてくれます。
一方で液体肥料は、速効性があるのが大きな特徴です。葉や茎の状態を見て「少し元気がない」「葉が黄色っぽい」と感じたときに与えると、短期間で効果が出やすいです。
特に、芽かき後から開花までの限られた期間に、即効性が求められるときに活躍します。
固形と液体をうまく使い分けることで、ジャガイモが安定して育ち、収穫量の増加につながります。
②有機肥料と化成肥料の特徴
肥料には「有機肥料」と「化成肥料」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
有機肥料は、動植物由来の成分で構成されているため、土壌の環境を改善する働きがあります。分解される過程で土がふかふかになり、微生物の活動も活発になります。
ただし、効果が出るまでに時間がかかるのが難点です。
一方で化成肥料は、成分が数値としてはっきりしており、効果が早く現れるのが特徴です。必要な栄養素をバランス良く含んでいるものも多く、ジャガイモの成長を計画的にコントロールしやすいメリットがあります。
つまり、有機肥料は「土づくり」や「長期的な効果」、化成肥料は「即効性」と「安定した成果」に強みがあります。
③緩効性肥料の効果
緩効性肥料は、ゆっくり長く効くタイプの肥料です。ジャガイモのように栽培期間が数か月に及ぶ作物では、緩効性の肥料がとても役立ちます。
例えば「ジシアンジアミド(Dd)」や「ウレアホルム(UF)」を含む肥料は、効果がじわじわと長期間にわたって続きます。そのため、一度与えると追肥の回数を減らすことができ、作業の手間が省けます。
また、急激に栄養が効かないため、肥料焼けや成長のアンバランスを防ぎやすい点も大きなメリットです。初心者の方にも扱いやすい肥料といえます。
栽培中に何度も肥料を追加するのが難しい場合には、緩効性肥料を上手に取り入れると安心です。
④有機と化成を組み合わせるメリット
「有機と化成を組み合わせる」方法は、ジャガイモ栽培にとても有効です。これを「有機ダブルセット」と呼ぶこともあります。
化成肥料の速効性で初期の成長をぐんぐん伸ばし、その後、有機肥料がじっくり効いてきます。結果として、栽培期間を通して安定した栄養補給が可能になります。
さらに、セットに含まれる「ミネラル材」は、マグネシウムや微量要素を含んでおり、光合成を助け、ジャガイモを健康的に育てます。これによって病気に強く、品質の良い芋に仕上がります。
つまり、化成肥料と有機肥料の「いいとこ取り」をすることで、失敗しにくく、美味しいジャガイモを収穫しやすくなるのです。
ジャガイモに適した肥料成分のバランス
ジャガイモに適した肥料成分のバランスについて解説します。
では、それぞれの栄養素について詳しく見ていきましょう。
①窒素は少なめに抑える
ジャガイモ栽培では、窒素(N)の量を控えめにすることが重要です。窒素は本来、葉や茎の成長を助ける栄養素ですが、多すぎると「葉ばかりが茂って芋が太らない」という結果を招きます。
窒素が過剰になると、見た目には立派な葉が生い茂っていても、土の中では芋が十分に育たず、小さくて水っぽい状態になります。さらに、病気や害虫に弱くなるというデメリットもあります。
そのため、ジャガイモ向けの肥料を選ぶときは「窒素控えめ」と書かれたものや、NPK表示で「Nが低め、PとKが高め」の配合を選ぶと良いです。
こうすることで、地上部と地下部のバランスがとれ、実入りの良い芋が育ちます。
②リン酸で根と芋を育てる
リン酸(P)は、ジャガイモにとって欠かせない栄養素です。根の発育を助け、芋の肥大化を促進する役割があります。
リン酸が不足すると、根の成長が不十分になり、芋に栄養が行き渡らなくなります。さらに、エネルギーの移動もスムーズにいかなくなるため、生育全体が遅れてしまいます。
ジャガイモ専用の肥料には、リン酸を高めに配合したものが多いです。特に「元肥」にしっかりリン酸を仕込んでおくと、根張りが良くなり、その後の芋の成長も順調に進みます。
リン酸は収穫量を左右する大事な要素なので、バランスの中心に据えて考えましょう。
③カリウムで病害虫に強くする
カリウム(K)は、植物全体の健康維持に欠かせない栄養素です。特にジャガイモでは、病害虫に対する抵抗力を高める効果があります。
カリウムを十分に与えると、イモがしっかり太り、でんぷん質も充実します。逆に不足すると、イモが小さく収穫量が落ちるだけでなく、病気にかかりやすくなるため要注意です。
ジャガイモ用肥料の多くは「カリ高め」のバランスになっています。NPKの表示で「K」がしっかり含まれているかを確認するのがポイントです。
また、カリウムは「茎葉からイモへ栄養を送る働き」にも関わっているため、収穫前のイモの品質に直結します。
④マグネシウムや微量要素の役割
マグネシウムや鉄、亜鉛などの微量要素も、ジャガイモ栽培では忘れてはいけない大事な成分です。特にマグネシウムは、葉の緑色を作るクロロフィルの成分であり、光合成をサポートします。
光合成がしっかり行われることで、ジャガイモは栄養を蓄え、芋にしっかりデンプンを送り込むことができます。マグネシウムが不足すると葉が黄化し、生育不良を引き起こします。
市販の「有機ダブルセット」や「ミネラル材」には、これらの成分がバランスよく配合されています。副資材として取り入れることで、栄養のバランスをさらに整えることができます。
ジャガイモを元気に、大きく育てたいなら、NPKだけでなく微量要素にも気を配るのが大切です。
ジャガイモ肥料の正しい与え方とタイミング
ジャガイモ肥料の正しい与え方とタイミングについて解説します。
それぞれのステップを押さえて、ジャガイモを効率よく育てていきましょう。
①元肥を植え付け前に仕込む
ジャガイモ栽培では、種芋を植え付ける「1週間前」に元肥を仕込むのが基本です。元肥とは、植え付け前に土に混ぜ込む肥料のことで、栽培の土台をつくる重要な役割を担います。
元肥には、固形肥料を中心にリン酸とカリウムを多めに配合したものを選びましょう。これにより、植え付け直後から根の成長と芋の発育をサポートすることができます。
培養土を使う場合、すでに元肥が配合されているケースもあります。その場合は、副資材としてマグネシウムや微量要素を追加して、よりバランスの取れた土壌に整えるのがおすすめです。
元肥をしっかり仕込んでおくことで、植え付け後の初期成長がスムーズになり、収穫量にも直結します。
②芽かき後に追肥をプラス
追肥のタイミングは「芽かきの後」です。芽かきは、植え付けから1か月ほど経ち、芽が10cm以上に育ったタイミングで行います。ここで良い芽を残し、不要な芽を取り除くことで、栄養が選ばれた芽に集中します。
芽かき後に追肥を行うことで、いよいよ始まるイモの肥大をしっかりサポートできます。追肥は、株元から少し離した場所に施し、軽く土となじませるようにします。
さらに、この追肥のタイミングで「土寄せ」もセットで行いましょう。土寄せは、ジャガイモの緑化や毒素の生成を防ぐ効果があり、品質を高める大事な作業です。
追肥は必ず開花前に済ませることが鉄則です。開花後に追肥すると、芋よりも茎葉に栄養が行ってしまい、芋が十分に育たなくなるので注意してください。
③土壌pHを5.5〜6.0に保つ
ジャガイモは土壌pHが5.5〜6.0の環境でよく育ちます。もしpHが7.0以上になると「そうか病」が発生しやすくなるため、必ず酸性寄りに調整しましょう。
植え付けの2週間前に苦土石灰や土壌改良材を土に混ぜ込むのが効果的です。これにより、土壌環境が安定し、根張りや肥料の吸収効率も高まります。
また、ジャガイモは中性やアルカリ性の土壌では育ちにくいので、定期的にpHを測定しておくと安心です。
正しいpH管理を行うことで、病気に強く、元気な株を育てられるようになります。
④排水性の良い土作りが重要
ジャガイモは排水性の悪い土では腐敗しやすく、育ちが悪くなります。そのため、土作りの段階で排水性をしっかり整えておくことが大切です。
畑の場合は、深さ30cmほどまで耕し、土をふかふかに仕上げます。腐植資材や堆肥を混ぜて団粒構造をつくると効果的です。また、排水が悪い土地では「高畝」にして栽培するのも有効です。
プランター栽培の場合は、深さ30cm以上のものを選び、底に軽石や鉢底石を入れて水はけを良くします。培養土は「野菜用」や「芋類用」を選ぶと、初めから適した排水性が確保されています。
排水性の良い土壌を準備しておくことで、根腐れや病害のリスクを減らし、ジャガイモが元気に育ちます。
肥料不足や過剰のサインと対処法
肥料不足や過剰のサインと対処法について解説します。
ジャガイモの状態を観察して、適切な対応をとりましょう。
①葉の黄化は肥料不足のサイン
ジャガイモの下葉が黄色くなってきた場合、それは肥料不足のサインです。特に、葉の色が全体的に薄い緑から黄緑に変化している場合は要注意です。
このような症状は、窒素やマグネシウムの不足で起こりやすいです。肥料不足のまま放置すると、光合成の能力が下がり、イモに十分な栄養が送られなくなります。
対応としては、速効性のある液体肥料を追肥として与えるのがおすすめです。芽かき後〜開花前であれば、株が元気を取り戻し、芋の肥大を助けることができます。
②茂りすぎは窒素過多
茎や葉がやたらと大きく茂っている場合、それは窒素が過剰になっているサインです。見た目には元気に見えますが、実際には芋に栄養が回っていない状態です。
窒素が多すぎると、芋が太らず、小さく水っぽい収穫物になってしまいます。さらに、茎葉が繁りすぎると風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。
このような場合は、追加の肥料は控え、追肥をストップすることが大切です。肥料は「少なめ」が基本で、与えすぎないことが成功へのポイントになります。
③小さく水っぽい芋は要注意
収穫したジャガイモが小さくて水っぽい場合、それは肥料のバランスが崩れている証拠です。特に、窒素の過剰が原因であることが多いです。
水っぽい芋はでんぷん質が少なく、食感や味も落ちてしまいます。また、病害虫にも弱いため、保存性も低くなってしまいます。
このトラブルを避けるためには、リン酸とカリウムを高めにし、窒素を抑えた肥料を選ぶことが大切です。肥料のバランスを見直し、次の栽培に活かしましょう。
④液体肥料で速効的に補う
肥料不足のサインが出たときには、液体肥料を活用すると効果的です。液体肥料は土や葉から素早く吸収され、短期間で株の状態を回復させることができます。
特に、開花まで時間がないときには液体肥料が強い味方になります。下葉の黄化や成長の停滞を感じたら、速効性のある液体肥料を与えてみましょう。
ただし、液体肥料も与えすぎには注意が必要です。ラベルに記載された量を守り、週に1回程度を目安に使うと安心です。
固形肥料と液体肥料をうまく組み合わせれば、急な不足にも対応しやすくなります。
ジャガイモ栽培で肥料を使うときの注意点
ジャガイモ栽培で肥料を使うときの注意点について解説します。
収穫を成功させるために、肥料を使うときの注意点を確認しておきましょう。
①窒素成分を与えすぎない
ジャガイモ栽培で最も気をつけたいのが「窒素の与えすぎ」です。窒素は葉や茎の成長を促す役割がありますが、過剰に与えるとイモに栄養が回らなくなります。
その結果、葉は青々と茂るのに、肝心の芋が小さく、水っぽくなってしまうのです。さらに、病害虫の被害を受けやすくなるというリスクもあります。
窒素は必要最低限で十分です。NPKバランスの「Nが低め、PとKが高め」の肥料を選ぶと安心です。窒素成分を抑えることが、収穫量と品質を高めるコツになります。
②開花後の追肥は控える
ジャガイモの追肥は「開花前まで」に済ませるのが鉄則です。開花後に肥料を与えると、茎葉を維持するための活動にエネルギーが使われてしまい、芋に栄養が行き渡らなくなります。
その結果、イモの肥大不良や奇形が発生することもあります。開花後の追肥は逆効果になるため、芽かき後から開花前の限られたタイミングで行いましょう。
ただし、追肥を行った後に開花するのは問題ありません。あくまでも「開花後に追肥を始める」のがNGという点を覚えておくと安心です。
③緑化を防ぐために土寄せする
肥料を与える際には「土寄せ」とセットで行うことが重要です。土寄せとは、株元に土を寄せて盛り上げる作業のことです。
この作業を行わないと、ジャガイモが地表に出て日光に当たり、緑化してしまいます。緑化したジャガイモには「ソラニン」「チャコニン」といった有害成分が含まれ、食用に適さなくなります。
追肥と同時に土寄せを行うことで、肥料の効果を高めると同時に、品質の良いジャガイモを収穫できるようになります。
④肥料シミュレーターを活用する
肥料の量は「多すぎても少なすぎてもNG」です。とはいえ、自分で正確に計算するのは難しいものです。そんなときに便利なのが「肥料シミュレーター」です。
肥料シミュレーターを使えば、土壌の状態や栽培面積に合わせて、最適な肥料の量を簡単に確認できます。初心者でも安心して施肥量を決められるので、失敗を防ぐために活用しましょう。
栽培を効率よく進めるためには、経験だけでなくツールの活用も大事なポイントです。
まとめ|ジャガイモ追肥時期を守って豊作に
これまで解説した「ジャガイモ追肥時期を見極めるコツ」を表にまとめました。
| ジャガイモ追肥時期のポイント |
|---|
| 芽かき後に与えるのが基本 |
| 開花前に追肥を終える |
| 土寄せとセットで行う |
| 追肥の量は控えめに調整 |
ジャガイモの追肥は「芽かき後、開花前」が最適なタイミングです。ここを逃さずに肥料を与えることで、イモの肥大が進み、収穫量と品質が大きく向上します。
また、窒素の与えすぎは禁物で、リン酸とカリウムを多めにした肥料が効果的です。肥料不足のサインや過剰のリスクも見極めながら、必要に応じて液体肥料を取り入れると安心です。
追肥と同時に土寄せを行い、緑化や毒素の発生を防ぐことも忘れずに。さらに、肥料シミュレーターを活用すれば施肥量を数値で確認でき、初心者でも失敗が少なくなります。
ジャガイモの栽培は、肥料の種類や与え方を少し工夫するだけで驚くほど結果が変わります。ぜひ実践して、豊作を実現してください。